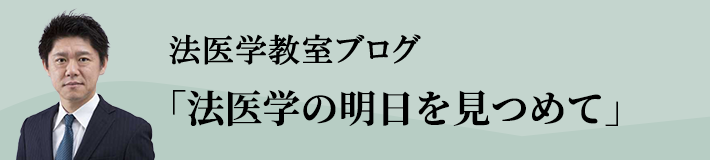法医解剖の知見を活かし、社会問題の解決に貢献します。

日本大学医学部 社会医学系法医学分野のホームページへようこそ
本分野は、1928年に本学医学科にて法医学講義が開始され、1951年に初代教授・上野佐先生のもと法医学教室が開設されました。その後、1985年より押田茂實教授が教室を主宰し、2020年以降は奥田貴久が教室運営を任されております。
当教室は、法医学の知識と技術をもって社会的使命と責任を果たすことを目指しています。中でも、予期せぬ死の死因を明らかにする法医解剖は最も重要な業務で、解剖を通じて死因や死亡推定時刻の鑑定を行っています。
加えて、突然死の病態生理、アルコール代謝酵素と臓器障害、ナノポアシークエンサーを用いた個人識別などの研究、法医解剖の疫学的知見の社会還元などのにも取り組み、社会医学系分野の一員として幅広く社会問題の解決に貢献しています。
2024年には日本法医学会より「法医認定医施設A」に認定され、教育・研究・実務の体制もより充実しました。今後も高い専門性を持つ人材を育成し、法医学を通じて社会に貢献してまいります。
TOPICS
- 2025/04/1
- 船越助教が着任しました。
- 2025/03/4
- 警視庁捜査一課より山口准教授に感謝状が贈呈されました。
- 2025/03/1
- 第563回日大医学会例会で青木助教が発表を行いました。
- 2025/02/28
- 奥田教授が科学研究費助成事業(基盤研究C)に採択されました。
- 2025/02/1
- Podcast番組 「キャリア探偵の事件簿」に奥田教授が出演しました。
- 2024/11/28-29
- 日本DNA多型学会第33回学術集会にて千葉正悦上席研究員が、「MinIONを用いたmtDNA全配列解読およびSTR多型解析の改良法について」を発表しました。
- 2024/10/26
- 日本経済新聞夕刊「親子スクール理科学」コーナーにて、千葉上席研究員と奥田教授の監修によるDNAでなぜ個人が分かる?4つの物質の並び方がカギ」が掲載されました。
- 2024/10/21
- PreBSLシンポジウムにて、阿部祐二氏、山田敏弘氏が講演しました。
- 2024/10/17
- PreBSLシンポジウムにて、木村もりよ氏が講演しました。
- 2024/10/12
- 第93回日本法医学会学術関東地方集会にて山口るつ子准教授が、「若年女性の特発性冠動脈解離の一剖検例」を発表しました。 さらに10件表示する