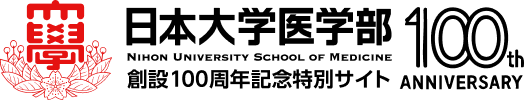ご挨拶
未来を担う医療人の育成と知の探求
日本大学医学部創設100周年に寄せて
第17代 日本大学医学部長
木下浩作
日本大学は,初代司法大臣・山田顕義先生を学祖とし,1889年に創設された日本法律学校を起源とする日本最大規模の総合大学です。日本大学医学部は,医学教育の近代化が求められた時代の要請に応え,創設者である額田豊先生の卓越した指導力と深い医療への情熱によって設立されました。額田先生は,当時急務であった専門的な医療人材の育成と医療技術の発展を強く信じ,大正14年(1925年)3月31日に設置認可を受け,日本大学専門部医学科としての開設に尽力されました。医学部は駿河台仮校舎でその歩みを始め,大正15年には附属病院が開院しました。額田先生は「医学は人間の幸福を実現する学問である」という信念のもと,単なる技術の習得ではなく,人間性を重んじる医学教育を実践されました。この精神は今日も日大医学部の教育理念の礎となり,後進に「医術とは人間性に裏打ちされた学問である」との教えが脈々と受け継がれています。 医学部の創設から100年の歩みは,医療技術の向上にとどまらず,医師としての倫理観や人としての役割を重視してきました。その結果,多くの優れた医師,研究者,教育者が巣立ち,世界各地で日大医学部の名声を高めています。特に医学研究の分野では,臨床に基づく基礎研究,新しい治療法の開発,医療技術革新における先端的な取り組みを進めるとともに,医学部附属板橋病院や日本大学病院では,地域医療への貢献とともに,救急医療や高度医療の提供に努めています。 日本大学医学部の100年の歴史は,卒業生,教職員,関係者,そして地域社会の皆様との深い結びつきと支えによって築かれたものです。医学部の卒業生たちは,単に医師としての技術を磨くだけでなく,「人々の命を守る使命感」を胸に日々努力を重ねています。これは,額田豊先生が残した最大の遺産であり,今日まで脈々と受け継がれている精神です。新しい時代においても,私たちは教育・研究・診療を通じて社会に貢献する医療人を育て,次の100年に向けてさらなる挑戦を続けてまいります。この場をお借りして,これまでの100年間,医学部を支えてくださった卒業生,教職員,関係者,地域社会の皆様に心より感謝申し上げます。今後とも変わらぬご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


医学部創設100周年を祝して
学校法人日本大学理事長
林真理子
日本大学医学部は今年,創設100周年を迎えました。心よりお祝い申し上げます。大正14年(1925年)3月,医学部は「日本大学専門部医学科」として東京・駿河台の地に産声を上げました。日本の医学界を長きにわたりけん引されてきた卒業生,教職員など関係者の皆さまのご尽力に深く敬意を表します。 本学は都内2カ所に医科系大学付属病院を有します。創設の翌年11月に開院した駿河台病院を前身とする日本大学病院は,千代田区で唯一の災害拠点病院であり,乗降客が一日100万人を超える東京駅を医療圏に持ちます。 また昭和45年(1970年)6月,東洋一の大学病院として開院した板橋病院は周辺人口190万人を擁する日本最大の医療圏に位置し,高度で先進的な医療を提供する特定機能病院・災害拠点病院として地域に貢献しています。 附属する看護専門学校はこれらの病院で最先端の看護実習を行い,やさしさ・倫理観・豊かな感性を備えた看護実践者を育成し,希望者の多くが2付属病院に就職しています。 今日まで質の高い医師,看護師を輩出し続けている医学部の教育理念は「醫明博愛」です。すべての人を平等に愛し,自己犠牲・献身を惜しまず,病める患者に真摯に向き合うという意味です。これは初代医学科長に迎えられた,額田豊博士の示した額田イズムの精神が脈々と受け継がれているものにほかなりません。 額田博士は「常識ヲ有シ人格アル実際的医師ヲ養成スルモノトス」という医師の明確な人間像を示して国に医学科設立の申請を行い,「人としての修養が十分でなければ如何に学問技術に長じていても患者の信頼を受くるものではない」と説いたほか,当時の世情に対し「やれ軍備だ,やれ戦争だと血眼になって騒ぐ人々よりも医学上の一業績を遂行した人の方がどれ程世界人類全般に対して幸福の泉を齎すことであろうか」と医学の尊厳と崇高性に言及しています。 世界は今激動の時代を迎えています。分断と対立の中,戦火が途切れることはなく,自然災害は年々激しさを増し,新興感染症の恐怖も一過性ではなくなっています。 この中にあって,地域に根差した災害拠点の中核となり,また,すぐれた医療従事者の育成という二つの使命を持つ付属病院の存在は,比類なき重要性を増していると確信しています。 次の100年を見据えれば,板橋キャンパスの再開発および新病院建設は,まさに時宜を得た英断であり,現在,オール日大でプロジェクトが着実に進行しています。 新病院は令和14年7月頃,地上6階,地下2階,約750~800床の大規模病院として生まれ変わります。 ハイブリッド手術も行える20室を超える手術室には手術支援ロボットが充実し,AI(人工知能)などのデジタルトランスインフォーメーション(DX)を駆使した新しいテクノロジーを導入するほか,患者とスタッフにゆとりとやすらぎを提供するスマートホスピタルを目指しています。ひいては地域との新たな架け橋としてまちづくりに貢献し,住民の安心・安全と健康を守る守護神として光を放ち続けることでしょう。 最後に,日本大学の魅力は,総合大学としてのメリットを生かした横のつながりです。全学を挙げて取り組んでいる医工連携プロジェクトではロボットやAIの活用を軸に,心臓組織の画像解析,乳がんの位置特定など幅広い共同研究を行っています。医学部と理工系学部が関わる大規模な連携を行っている総合大学はあまり例がありません。 今後は自然科学だけでなく,人文科学や芸術分野など多様な学部や企業との「知」の交流を積極的に進め,日本大学のポテンシャルである「総合知」をより強力なツールに育て上げてください。 来る100年,200年は日本大学医学部にとっても新たな価値の創造が問われる時代です。日本の医療をリードし,世界に飛躍する日本大学の中核としてさらに発展することを祈念し,私からのご挨拶と致します。
医学部創設100 周年を祝して
日本大学学長
大貫進一郎
日本大学医学部の創設100周年,誠におめでとうございます。日本大学の教学部門を代表し,心よりお慶び申し上げます。大正14年(1925年)3月に「日本大学専門部医学科」が神田駿河台に誕生してから一世紀,国民のみなさまの健康増進に貢献し,国内外の医学界で高く評価され続けてきたことにあらためて敬意を表するとともに,関係各位のご尽力に心より感謝を申し上げます。また,この記念すべき年に,これまでの歩みをまとめた「100周年記念誌」を刊行されますことは,わが国の医学史という点において大変意義深いことであると存じます。 日本大学は,学祖山田顕義が欧米視察での経験から「日本法学」の必要性を感じて「日本法律学校」を創設したことがその礎となりますが,医学部もまた,初代医学科長の額田豊先生のドイツ留学経験がその源流となります。今回の執筆にあたり,あらためて『日本大学百年史』等で足跡を辿らせていただきました。 額田先生は明治40年(1907年)3月に渡独され,2年3カ月の間にブレスラウ大学(現在のヴロツワフ大学)とミュンヘン大学で学ばれました。1702年に設立されたブレスラウ大学は,中央ヨーロッパ最古の大学のひとつであり,額田先生が帰国された後の1912年からはアロイス・アルツハイマーも精神科教授に就任しています。また,ミュンヘン大学は,ヨーロッパを代表する大学のひとつであり,額田先生が学ばれた同時期には,X線の発見者で第1回ノーベル物理学賞受賞者であるヴィルヘルム・レントゲンも教鞭をとっていたようです。このような最高峰の教育・研究機関に学んだだけでなく,日々の生活の中でドイツ人,特にドイツ人女性の,教養の高さや科学的な思考法に感銘を受けた額田先生は,教育への想いを強くされました。 帰国後の明治43年(1910年),額田先生は,胃潰瘍を患った夏目漱石を診察したことで,世に広く名が知られるようになります。その後,留学の経験を額田病院と額田保養院の開業をとおして実践され,また『婦人画報』や新聞,書籍といった媒体をとおして情報発信にも尽力されましたが,すべては学校開設のためであったともいわれています。そうした中,総合大学としては専門部歯科(現・歯学部)だけでなく医学部が必要であると考えていた平沼騏一郎総長,山岡萬之助学長らの想いと,かねてから抱いていた額田先生の教育に対する想いとが一致し,満を持して四年制専門学校である専門部医学科が誕生しました。 大正デモクラシー期の当時は,民主国家としての体裁が整えられつつありました。しかし,医療においては圧倒的に医師が不足し,特に,無医村の弊害も社会問題化して新たな臨床医の育成が急務であったことから,同医学科では臨床教育に重きを置くこととなりました。この方針は,現在は「よき臨床医の育成」と表現され,受け継がれています。また,設置目的には「常識を有し人格ある実際的医師を養成するものとする」という文言が盛り込まれました。これは,学問だけできればよいわけではないという額田先生の理念が反映されたもので,その後も100年にわたって,医学に留まらない広い知見の涵養と人間教育を実践し,社会から求められる「高い人間力を有する医師」を輩出し続けていることを,私は誇りに思います。 この一世紀で,社会は大きく変化しました。特に,コロナ禍以降,デジタル化の大きな波が押し寄せています。令和10年(2028年)には新学部棟が竣工予定となっており,最新の施設・設備とともに,Society 5.0で活躍する医療人が育っていくことを大いに期待する一方,デジタル全盛の社会であればこそ,人と人との真のつながり,そして周囲の人びとへの「愛」をたいせつにしていただきたいと考えています。先達の想いをつないだ教育理念「醫明博愛」を胸に,今後益々医学部が発展されることを願い,祝辞とさせていただきます。