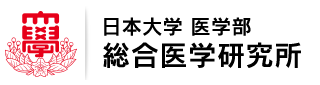- 研究紹介
- インフルエンザウイルスと口腔・気道細菌との相互作用の機序と呼吸器疾患重症化の病態
インフルエンザウイルスと口腔・気道細菌との相互作用の機序と呼吸器疾患重症化の病態
研究代表者:山本樹生
インフルエンザは、高齢罹患者において重症化率・致死率が著しく高まることが知られており、高齢化社会を迎えている日本では、インフルエンザに対する有効な対策の確立は喫緊の課題と考えられる。特に、インフルエンザ重症化の機構の解明は、高齢患者の救命率の上昇につながることが期待される。そこで、インフルエンザの病態悪化の機構を解明し、有効な対策を提案することが本プロジェクトの目的である。平成22年のプロジェクト開始から、着実な成果を蓄積できたと考えている。本プロジェクト前半期における最重要課題は、口腔・気道の細菌や体液中阻害因子がインフルエンザウイルス感染にどのような影響を与えるかを明らかにすることであったが、この目的はほぼ達成され、後半期においてさらに進展が見られた。インフルエンザ重症化のメカニズムに関しても重要な知見が蓄積された。
以下、成果の概略を記す。
- Ⅰ.インフルエンザウイルスと口腔・気道細菌との相互作用
- a ノイラミニダーゼ(NA)分泌口腔・気道細菌の同定を行った。
- b 細菌NAがウイルスNAの代わりにウイルス放出に働くことが示した。
- c 唾液中インフルエンザウイルス阻害物質が存在することを示した。
- d インフルエンザNA阻害薬の効果に対する細菌由来ノイラミニダーゼの影響を検討しNA阻害薬の効果は細菌由来ノイラミニダーゼ存在下では著しく減弱することを示した。
- e 鼻粘液には抗インフルエンザウイルス活性があることを証明した。
- f 細菌由来ノイラミニダーゼがインフルエンザウイルス感染を促進することを証明した
- g NAおよびHA遺伝子上の連動変異による機能的新型インフルエンザウイルスの出現することを証明した。
- Ⅱ.インフルエンザ重症化の病態解明
- a NS1遺伝子点突然変異により弱毒性インフルエンザウイルスの強毒化を証明した
- b 強毒インフルエンザウイルスによるサイトカイン産生の高進が認められることを示した
- c インフルエンザウイルスのNS1がポリA部位切断反応を阻害することで選択的スプライシングを引き起こすことを示した。
- d インフルエンザ脳症の病態として,髄液中のIL10やTNFαの上昇を伴わないIL6の上昇が観察された。またインフルエンザ感染後に抗GQ1b抗体陽性を伴うミラー・フィッシャー症候群やオプソクローヌス・ミオクローヌス症候群の合併が新たに認められた。
- e 妊娠とインフルエンザ: インフルエンザウイルス感染マウスモデルにおいて、母獣、胎児への影響を検討した。胎児重量に関しては、非接種群に比べ50%程度の減少が観察された。妊娠マウスのインフルエンザウイルス感染における体内サイトカインの変化では、重症例ではIL6, など炎症性サイトカインの異常高値、Treg細胞の異常高値が認められた。
- e インフルエンザ重症化に係る慢性呼吸器疾患の検討を行い: 重症化には気道のバリア障害が関係していることが指摘されている。PCDH1分子が気道のバリア機能障害に大きな役割を果たしていることが明らかとなった。さらに、感染の重症化因子として、上皮細胞間のタイトジャンクションがTLR3/TRIF経路を介して障害を受けること,NDRG1の機能の変調がこの障害に関与することがわかった。逆にステロイドやTLR9リガンドがタイトジャンクション形成促進作用を持ち,治療に資する可能性が示唆された。
- Ⅲ.口腔管理(口腔ケア)のインフルエンザ対策としての有効性の検証
口腔管理の有効性を検証するために、インフルエンザ罹患者の咽頭ぬぐい液中のインフルエンザウイルスと細菌の解析を行った。口腔ケアにより口腔内細菌数が顕著に減少し、細菌数の減少とインフルエンザ罹患率の減少の相関性がで示された。 - Ⅳ.その他の関連研究
ベトナムにおけるインフルエンザ流行状況を検討した。
ベトナム由来のウイルスが独自に位置にあることが示された。
参加者
- 相澤 信1)、
- 橋本 修2)、
- 松本 太郎3)、
- 槇島 誠4)、
- 田中 寅彦4)、
- 古阪 徹5)、
- 池田 稔5)、
- 高橋 昌里6)、
- 麦島 秀雄6)、
- 高山 忠利8)、
- 森山 光彦9)、
- 亀井 聡10)、
- 根本 則道11)、
- 杉谷 雅彦11)、
- 増田しのぶ11)、
- 江角 眞理子11)、
- 石原 寿光12)、
- 早川 智13)、
- 黒田 和道13)、
- 清水 一史14)、
- 中山 智祥15)、
- 安孫子 宜光16)、
- 落合 邦康16)、
- 柴田 恭子17)、
- 石原 和幸18)、
- 花田 信弘19)
- 1)機能形態学系生体構造医学分野、
- 2)内科学系呼吸器内科学分野、
- 3)機能形態学系細胞再生・移植医学分野、
- 4)生体機能医学系生化学分野、
- 5)耳鼻咽喉・頭頸部外科学耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野、
- 6)小児科学系小児科学分野、
- 8)外科学系消化器外科学分野、
- 9)内科学系消化器肝臓内科学分野、
- 10)内科学系神経内科学分野、
- 11)病態病理学系人体病理学分野、
- 12)内科学系糖尿病代謝内科学分野、
- 13)病態病理学系微生物学分野、
- 14)産婦人科学系産婦人科学分野、
- 15)病態病理学系臨床検査医学分野、
- 16)日本大学歯学部細菌学講座、
- 17)日本大学松戸歯学部生化学教室、
- 18)東京歯科大学歯学部 歯学科、
- 19)鶴見大学歯学部探索歯学講座